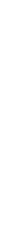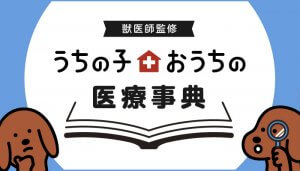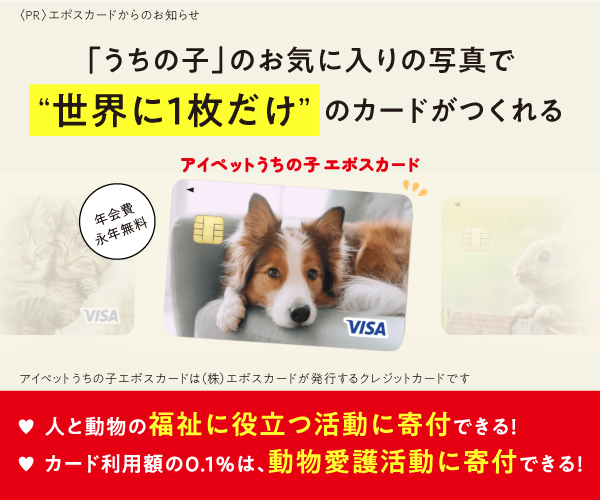攻撃行動とは?
犬の攻撃行動は、その対象が人間の場合、重篤な被害を招きやすく、結果的に犬を手放したり、安楽死を選択せざるを得ないケースに発展する可能性が最も高い問題行動の一つです。攻撃対象は人間だけではなく、同じ犬や他の動物が対象となったり、物が対象となったりするケースもあります。いずれにしても、被害を受けた側はもちろんですが、攻撃をした犬にとってもダメージがとても大きいといえる攻撃行動は、獣医師が早期に取りかかる必要のある問題行動の一つだと思われます。実際に、問題行動の相談の中で圧倒的に多いのが攻撃行動です。
攻撃行動に犬種差ってある?
「うちの犬はおとなしい犬種だから咬むなんてあり得ない」と安心しきっていませんか。犬の攻撃行動には、犬種によって違いがあるわけではありません。どの犬種であっても、攻撃行動が発現する可能性があることを常に頭に入れておかなければなりません。例えば、どうしても避けられないような状況に陥った場合、それを避けるために本能的に攻撃を発現する可能性はどの犬にもあるのです。
ただし、近年の研究で、攻撃性には遺伝が深く関わっていることも報告されていますので、特定の犬種や血統によっては、攻撃性がより強く現れやすいことがあります。

最初は威嚇行動から
犬の攻撃は、基本的には威嚇から始まります。例えば、
-
体を硬直させる
-
相手をにらみつける
-
唸る
-
吠える
-
歯を剥き出す
といった行動です。こういった威嚇行動から、空咬みをする、飛びつく、咬むなどといった実際の攻撃行動に発展していきます。
実は、攻撃の前段階であるこの威嚇行動は、犬が訴えるサインとして、とても重要だと思っています。私が以前飼っていた犬は、散歩中に挨拶をした犬が苦手だなと思った途端、体を硬くし、歯を剥き出して威嚇をすることがありました。最初の頃、私は威嚇すること自体を叱って、リードを強く引いていたのですが、叱られたことによって犬の緊張は取れないまま、悪いイメージを植え付けてしまっていたように思います。
そこで私は、威嚇は「もうやめて! 近づかないで!」というサインだと理解して、威嚇が始まった時には、優しく名前を呼び、ちょんちょんとリードを引いて合図を送り、さりげなく相手の犬から距離を取るようにしました。もちろん、私の方を向いた時点で思いっきり褒めてあげました。
そうしていくうちに、犬と会っても極端に緊張することが少なくなっていきました。私自身も、自分の犬のサインに気づき、その時にどうすればよいのかがわかったおかげで、他の犬と挨拶をする際に緊張しすぎることがなくなりました。飼い主の緊張は犬に通じるので、このことも影響を与えていたのかもしれません。
けれども、それぞれの犬によって、また攻撃をする原因によっては、威嚇行動が省かれて、いきなり攻撃行動が起きることもありますので注意が必要です。
攻撃行動の診断
獣医師が行動治療を行う場合、まずはその問題行動の原因を考えます。これは攻撃行動に限ったことではありません。少し難しい話になってしまいますが、動物が行動を起こす原因を「動機づけ」と言い、動物が行動を起こす際には、その動物に何らかの動機づけが働いていると考えられています。攻撃行動も、ある動機づけによって起こっていると考えられることから、まずはその動機づけを推測することから始まります。
残念なことに、「何で攻撃したの?」と、犬に直接尋ねることはできませんので、実際には飼い主さんからさまざまな情報を得ることがとても重要になってきます。カウンセリングを行いながら、どのような状況で攻撃が起きるのか、誰に(何に)対して攻撃が起きるのか、攻撃が起きた時に飼い主さんはどのような対応をしたのか、その時の犬の反応はどうだったか、などを詳細に聞いていきます。
さらに、攻撃行動そのものについてだけではなく、その犬が育ってきた環境や現在の生活環境はどうなのか、過去にトラウマとなるような経験をしなかったか、といったことまで考える必要があります。もちろん、これまでにかかったことのある病気や怪我、そして現在かかっている可能性のある病気などについても検討して、これらが攻撃の原因になっていないかどうかも判断します。

攻撃行動の動機づけによる分類
攻撃行動はその動機づけによって、さまざまな種類に分類されます。獣医師は上記のようなステップを経て、攻撃行動を分類して診断していくのですが、飼い主さんが攻撃行動の相談に訪れる段階では、すでに問題が複雑になっていることが多いため、実際には複数の診断名がつけられることは珍しいことではありません。
例をあげてみますと、
-
自己主張性攻撃行動
-
恐怖性/防御性攻撃行動
-
葛藤性攻撃行動
-
捕食性攻撃行動
-
縄張り性攻撃行動
-
所有性攻撃行動
-
転嫁性攻撃行動
-
疼痛性攻撃行動
-
母性攻撃行動
-
特発性攻撃行動
…などなど、本当にたくさんの動機づけがあります。獣医師によって使用する名称は多少異なったりはしますが、動機づけの考え方は基本的に変わりません。
次回からのコラムでは、それぞれの攻撃行動について、実際の症例もご紹介しながら、出来るだけわかりやすく解説していきたいと思います。
犬の「攻撃行動」に関する獣医師監修記事
□ 第1回 犬が威嚇をしてくるのはなぜ?
□ 第2回 家族に対して犬が攻撃行動を取る理由
□ 第3回 不安からくる犬の攻撃行動
□ 第4回 犬がなにかを守ろうとするときの攻撃行動
□ 第5回 多頭飼いでは犬の順位付けに気を付けて!
□ 第6回 病院で暴れるワンちゃんは何が原因なの?
●「犬の気持ち」に関する記事
□しっぽ:犬の“しっぽ”で感情を読み取ろう!
□ 見つめる:じーっと見つめてくるときの犬の気持ちは?
□ しぐさ:行動学の専門家が解説!仕草からわかる犬の気持ち
□ 鼻舐め:犬が鼻をペロペロ舐めるのはなぜ?
□ 他の犬:他の犬に会った時、愛犬はなにを考えているの?
□ 威嚇:犬が威嚇をしてくるのはなぜ?
□ 順位付け:多頭飼いでは犬の順位付けに気をつけて!
□ 好き嫌い:愛犬の好きなこと、苦手なこと、
□ 転移行動:犬が自分のしっぽを追いかけるのはなぜ?
□ ストレスサイン:犬のストレスサインとは?どんな行動をするの?
●「しつけ」に関する記事
□ アイコンタクト:全てのしつけに必要!愛犬とのアイコンタクト
□ 失敗談:みんなのしつけ失敗談。先輩の失敗から学ぼう!
□ 子犬:子犬を迎えたばかりのお家は要注意!そのしつけ、
□ ドッグカフェ:ドッグカフェでいい子にしてもらうためのしつけ
□ おいで:呼んだら来てくれる「おいで」のしつけ
□ 待て:犬のしつけ「待て」はとっても重要!
□ 咬み:噛む犬のしつけ方
□ 吠え:犬の無駄吠えのしつけ方 <原因別に解説>」
□ クレート:クレートを好きになってもらってお留守番上手に
★「うちの子」の長生きのために、気になるキーワードや、症状や病名で調べることができる、獣医師監修のペットのためのオンライン医療辞典『うちの子おうちの医療事典 』をご利用ください。
例えば、下記のような切り口で、