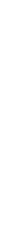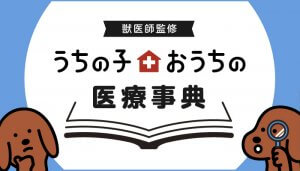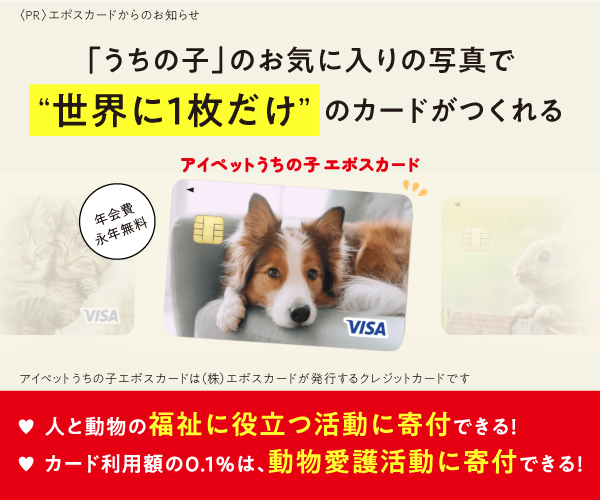人間には血液バンクがありますが、犬の血液を保存しておく血液バンクは現在、日本にはありません。それでは、犬が事故や病気のために輸血を必要とした場合はどうするのでしょうか?万が一のときのために、供血犬という存在を知っておきましょう。
供血犬とは何をする犬?

供血犬という耳慣れない呼び名、じつは血液が必要な犬のために献血してくれる犬のことをさします。病院によっては供血犬を飼育しているところもありますが、一般的には必要な際に飼い犬に献血をお願いして血液を確保するケースが多いようです。
ちなみに1回の採血量は150ml〜200ml程度です。
※レシピエント(輸血を受ける犬)が小型犬の場合は、より少ない量の採血ですむこともあります。
そもそも犬に血液型はあるの?

犬の血液型はDEA方式で8種類
犬にも血液型はあり、DEA式(Dog Erythrocyte Antigens/犬赤血球抗原)で分類されます。人間の血液型は、A、B、AB、Oの4種類ですが、犬の場合は「DEA1.1」「DEA1.2」「DEA3」「DEA4」など全部で8種類に分かれています。
その8種類にはそれぞれ抗原の有無「+」「-」があり、さらに1頭が複数の抗原を持つので、「DEA1.1(−)」「DEA1.2(+)」「DEA3(−)」というように複雑な血液型分類となります。じつは犬の血液型はまだ研究段階にあり、現在のところ全部で13種類以上の血液型があると考えられています。詳しくは「【獣医師監修】犬にも血液型はあるの?犬の血液型と性格の関係は?」をご覧ください。
輸血前に血液型適合検査を実施
犬に輸血する場合、初回は血液型が一致していなくてもあまり問題はありませんが、2回目以降や咬傷の経験がある場合は、体内にできた抗体が拒否反応を示すことがあります。そのため、輸血前に血液適合検査をきちんと行う必要があります。
供血犬になる条件とは?ドナー登録の方法は?

採血した犬の血液は長期間保存しておくことができないので、必要に応じて供血犬から採血するか、ドナーから採血して血液を集めるしかありません。もし愛犬が下記の条件を満たし、飼い主さんが「ほかの犬の命を救うために、役に立てるならば」と思ってもらえるなら、かかりつけの動物病院でドナー登録の有無を聞くか、日本動物高度医療センター(JARMeC)などドナーを募集している動物病院に連絡してみてください。
登録条件
供血犬になる条件は病院によって多少違いがあるようですが、おおよそ以下のような内容になっています。
年齢1歳〜8歳未満
体重15kg以上
狂犬病予防接種、混合ワクチン摂取、フィラリア予防を毎年受けている健康な犬
麻酔をかけずに採血できる温厚な性格
献血前に身体検査と血液検査
献血の際には、獣医師による身体検査と血液型の検査を受けます。その結果、献血を行っても問題がなければ、採血(体重1kg当たり10〜12mlが目安)を行います。かかる時間は15〜30分程度です。
なお、犬の健康を守るために一度献血をしたら、3〜4週間空けないと次の献血はできません。輸血を受ける犬の血液型との適合性を考えても、多くのドナー登録があったほうが助けられる命が多くなると言えます。
献血ができない犬の条件とは?
以下に該当する犬は、残念ながら献血はできません。
過去に輸血を受けた経験がある犬
過去に妊娠および出産を経験している犬
全身性の重度感染性皮膚疾患がある犬
過去に血液媒介性の感染症(バベシア症、犬ブルセラ症など)にかかった、もしくはかかった疑いのある犬
秋田犬およびその交雑種(秋田犬は赤血球内のカリウムの濃度が高いため)
各病院が万が一に備えて供血犬を飼育しておくのは難しく、善意のボランティアによる献血ドナーに頼らざるを得ないのが現状です。緊急時に飼い主さんが自力で、献血してくれる犬を探さなければならないという話もよく耳にします。供血犬の存在を知ったことをきっかけに、ドナー登録について詳しく知りたいと思った飼い主さんは、ぜひ動物病院に問い合わせてみてください。
★愛犬の「お世話」に関するワンペディア記事
愛犬のお世話の方法をさらにレベルアップするための関連記事をご
□ トリミングの目的:意外と知らない、
□ 自宅でトリミング:初心者でも簡単!自宅でできるトリミング【
□ バリカン講座:初心者向けのバリカン講座!
□ ブラッシング:獣医師が解説!犬の正しいブラッシング」
□ 足裏ケア:もうフローリングで滑らない!愛犬の足裏ケア」
□ サロン選び:優良なトリミングサロンを選ぶ6つの基準」
□ 耳掃除:【獣医師監修】犬の耳掃除。
□ シャンプー:愛犬がシャンプー好きに!正しい頻度と洗い方【
□ 毛並み:愛犬の毛並みを良くするためのお手入れ【獣医師解説】
□ お手入れまとめ:愛犬に必要なお手入れまとめ
★うちの子の長生きのために、気になる病気について簡単に調べることができる、「うちの子おうちの医療事典」もご活用ください。
★「ワンペディア編集部」では、愛犬との暮らしに役立つお勧め記事や、アイペット損保からの最新情報を、ワンペディア編集部からのメールマガジン(月1回第3木曜日夕方配信予定)でお知らせしています。ご希望の方はこちらからご登録ください。