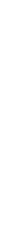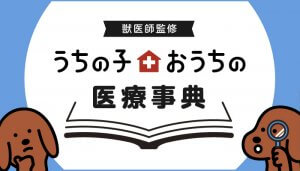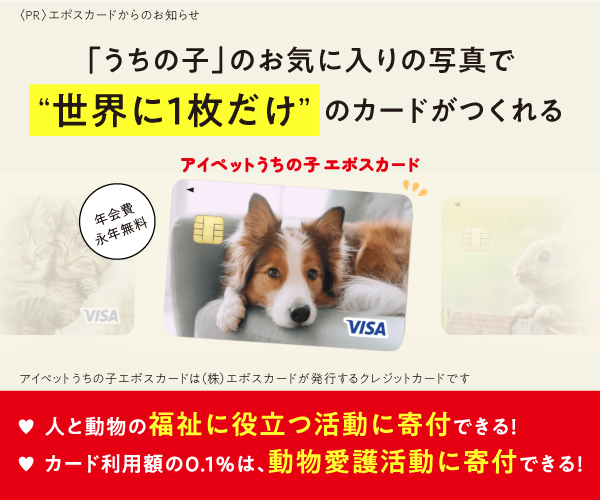散歩のときはもちろん、家の中やアウトドアで犬の行動範囲を規制したいときや、車の中で安全にドライブを楽しみたいときなど、いろいろな場面で活躍してくれるのが「リード(引き綱)」です。
ペットショップではさまざまな種類のリードが販売されていて、どれを選んだらいいのか迷ってしまう人もいることでしょう。失敗しないリード選びのコツをご紹介します。
リードの役割とは?
リードはただ単に犬をつなぎ止めておくためだけのものだと思っている方はいませんか? 実はもっと大事なリードコントロールの役割も担っているのです。リードコントロールとは
リードを通じて飼い主さんの意思を伝えること
です。それぞれの犬にあった長さや素材のリードを選ばないと意思を伝えることが難しくなってしまいます。種類が多くて大変だと思いますがしっかりと愛犬にあったリードを選びましょう。
リードの種類は?
スタンダードリード
一方が円形で飼い主さんの持ち手となっており反対側が犬の首輪やハーネスとつなげるように金具が付いています。一般的に通常の散歩のときに使われ長さは120㎝ら150㎝のものが多くなっています。素材の種類が多いためたくさんの種類の中から選ぶことができることも特徴です。
フレキシブルリード(伸縮性リード)
手元のスイッチでリードを伸ばしたり巻き戻したりできるリードです。公園など広く危険のない場所で使用することに向いています。犬を自由に歩かせることができる一方でコントロールが難しくなるという欠点もあるので道路のお散歩ではあまりおすすめできません。
トレーニングリード
「ロングリード」とも呼ばれ10メートルから長いものだと25メートルにもなります。こちらも長く犬のコントロールが難しくなるためフレキシブルリードと同様に公園などで使用しましょう。距離をとることができるため「おいで」の練習に適しています。
マルチファンクションリード
名前の通り様々な機能を持ち合わせたリードです。タスキのように肩から掛けられたり、一時的に犬をつないでおくためのループを作ることもできるようになっています。素材やデザインもたくさんの種類があるため自分好みのものを選ぶことができるのことも魅力の一つといえるでしょう。
リードの太さはどのくらいがいい?
実は、リードには「適正体重」が設定されています。そのため愛犬の大きさにあった太さを選ぶ必要があります。ほとんどのリードは、適正体重が軽ければ細く、重ければ太く作られています。
細いリードのほうがスマートに見えるからカッコいい、細いリードのほうが安い、などの理由で選んではいけません。
もし大型犬が小型犬用のリードを使ってしまうと犬がダッシュしたときなどにリードが切れたりフックが壊れたりして重大事故につながる可能性があります。
また、同じ太さでもリードの素材によって適正体重は異なってくるので気をつけましょう。
リードの長さはどのくらいがいい?
リードの長さの種類は?
リードの長さは1m未満のショートタイプ、1m台のスタンダードタイプ、2~3mのミドルタイプ、5mなどのロングタイプに大きく分けられます。このうち、スタンダードタイプが一番主流です。
どのように選べばいいの?
リードは自分が犬にどのくらいの範囲で自由にさせたいかを基準にして選びましょう。
ショートリード
ひっぱり癖や無駄な動きの多い犬はショートリードを使い飼い主さんがしっかりと犬の動きをコントロールしましょう。このような犬に
長いリードを使うと急に犬が走りだしたとき飼い主さんが止めることが出来ずに事故につながる
こともあります。
スタンダードタイプ
一番主流の長さのリードです。飼い主さんから逃げないようにしっかりとしつけの出来ている犬の散歩に使用しましょう。
ミドルタイプ・ロングタイプ
2メートル以上のリードはコントロールが難しくなるため道路では使用しないでください。郊外や広場など広く危険の少ない場所で走り回ったり自由に動けるようなときに使ってあげましょう。犬にとってはノーリードのようになるのでおもいっきり遊べます。
リードの素材は何がいい?
リードの材質は、大きく「布」「金属」「革」「ナイロン」「ラバー」に分けられます。それぞれの材質の特徴を理解して愛犬にぴったりのリードを選びましょう。
布製リード
色がカラフルでデザインも多種多様、比較的安価で軽く使いやすいのがメリットです。汚れても洗濯できますし、リード端の輪っかのホールド感もよく、リードコントロールもしやすいのでおススメです。迷ったらこのタイプを選んでおけばいいでしょう。
金属リード
とにかく丈夫なのが最大のポイント。物をかじる癖がある犬でも安心して使えます。見た目がワイルドなので、ブルドッグやボクサーなどに装着するといかにも強そうです。ただし丈夫な反面、重さがあるのでリードコントロール時に飼い主さんが手を傷めやすい傾向も。また金属の性質上、しっかりお手入れをしないと錆びてしまったり金属アレルギーが出る可能性もあります。
革製リード
見た目の高級感と、しっとりした手触りが特徴。革自体に適度な伸縮性があるため、散歩時のリードコントロールが心地よく行えます。難点は価格が高価になりがちなことと、おもちゃ代わりに噛んでしまう犬がいることです。
また、水に弱いこともデメリットの一つとしてあげられます。雨の日に使うことで傷んだりカビが生えたりしてしまいます。噛まれて傷ついた革製リードは意外にあっけなく切れてしまいますし、自然素材のため経年劣化も大きく、突然ブチッと切れてしまうことも。革製のリードを使用する際はこまめに掃除、点検をし清潔に保ちましょう。
ナイロン製リード
耐久性が高く劣化しにくい素材です。金属リードや革製リードと比べると比較的軽いため飼い主さんの負担は少ないというメリットもあります。一方で、静電気が発生しやすいので冬場は注意が必要です。
リードは毎週1回の状態チェックをおすすめします。亀裂などがあると、ちょっとした衝撃にも耐えられず、その部分から切れてしまいます。ある程度使ったら新品のものに交換しましょう。
また、リードを正しく使うためには、基本的な持ち方をマスターしておく必要があります。「犬のお散歩、飼い主が心得ておくべきこととは」ちらの記事で解説していますので読んでみてください。
犬の「散歩」に関するワンペディア記事
□ 散歩時間の見極め方:「犬のお散歩、
□ 喜ぶ散歩:「作業的なお散歩はやめて! 愛犬が喜ぶお散歩とは」
□ 雨の日の散歩:「雨の日の犬のお散歩、どうしてますか?」
□ 歩かない犬の散歩「歩かない犬との散歩、どうしたらいいの?」
□ シニア犬の散歩:「犬はシニアになってもお散歩が必要? 散歩時間の目安は?」
★うちの子の長生きのために、気になる病気について簡単に調べることができる、「うちの子おうちの医療事典」もご活用ください。
★「ワンペディア編集部」では、愛犬との暮らしに役立つお勧め記事や、アイペット損保からの最新情報を、ワンペディア編集部からのメールマガジン(月1回第3木曜日夕方配信予定)でお知らせしています。ご希望の方はこちらからご登録ください。

アイペット獣医師
詳細はこちら