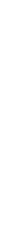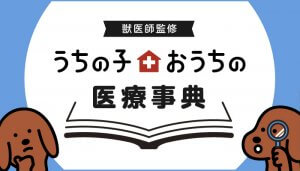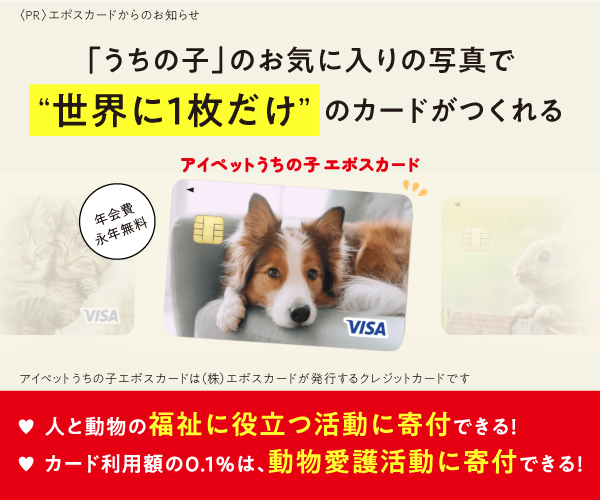愛犬が道路や床に落ちているものをすぐに咥えてしまったり、キッチンの下でクンクンやっているとヒヤヒヤしますよね。特に子犬のときは好奇心が旺盛で、なんでも口に入れたくなる時期。本当は食べたらいけないものを、もしも食べてしまったら、異物誤飲などのケガや中毒症状を引き起こす可能性もあります。愛犬の健康を守るためにも、拾い食いをやめさせるトレーニングが必要なのです。
拾い食いで起こり得るトラブル
中毒を引き起こす食品は死に至る可能性も
タマネギ、チョコレート、レーズン、ぶどう、人間の薬などは犬に重篤な中毒症状を引き起こすことがあります。また、害獣駆除用の毒餌を散歩中の犬が食べてしまい死亡するというニュースもありました。犬が生活する上で危険なものは、実は身近たくさんあるのです。
*中毒症状を引き起こす食べ物についてはこちらをご覧ください。
先の尖った串やビニールを飲み込み開腹手術に
焼き鳥の串や割り箸、食べ物が入っていたビニール袋などを飲み込んでしまって消化器官を傷つけたり、異物が消化されずに胃や腸に詰まってしまったりすると、手術をしなければならなくなります。犬は食べ物ではないものも口にする場合があるので、気をつけなければなりません。「犬が異物誤飲をしたとき、どうしたらいいの?【獣医師解説】」も併せてご覧下さい。
拾い食いのトレーニングを始める前に
落ちているものを拾って食べたときに叱るのではなく、
落ちているものを食べなかったときにほめて
あげましょう。ほめられたほうがトレーニングもがんばれます!
拾い食い防止トレーニングのために準備するもの
■ 愛犬が大好きなおやつ(カロリーの少ないもの)
■ リードと首輪、もしくはハーネス
集中できる環境をつくる
犬の集中力は10~15分と短時間です。最初は集中しやすいように、静かな環境ではじめましょう。テレビなど、気が散るものがないようにしてください。1日で覚えられるわけではないので、15分が経過したら一旦そこでトレーニングを終了しましょう。
犬に首輪(もしくはハーネス)とリードを付ける
犬を一定の範囲内しか動けないようにします。人がリードを持って行ってもいいですが、中型犬以上では力で負けてしまうこともあるので、どこかに結びつけるなどして固定してください。
拾い食い防止のトレーニング方法
アイコンタクトをしたらごほうび

まず、
犬をリードで固定したまま、届きそうで届かない床におやつを置きます。
最初、犬は自力で取ろうとがんばりますが、そのうち自分の力では取れないということに気がつきます。
このような状態になったら、あとは愛犬からアイコンタクトがくるのを待つだけ。
愛犬が飼い主さんの方を向いたら、ごほうびをあげて
ください。
「待て」という言葉を使います
愛犬がアイコンタクトになれてきたら、次は「待て」「おあずけ」などの言葉を使いましょう。先ほどと同じようにリードで犬を固定し、おやつを置いたら、
愛犬が飼い主を見る前に「待て」「おあずけ」等の号令
をかけます。
「号令」→「アイコンタクト」→「ごほうび」を繰り返し練習します。
リードをはずしてやってみよう!
リードを外して犬の近くに食べ物をおき、「待て」「おあずけ」等の号令をかけてみましょう。食べられる状況を理解しているのにも関わらず、ちゃんと我慢してアイコンタクトをしてきたら成功です!
指示を無視して食べてしまったら、またリードをつけてやり直し
てください。大事なのはここで失敗しても怒らないこと。根気よく続けてあげてくださいね。
ごぼうびの回数を減らす
リードをしていなくても指示に従えるようになったら、今度はごほうびの回数を減らしていきます。
減らし方は犬が予測出来ないよう、ランダムに。
ごほうびがあってもなくても、号令だけで動けるように練習します。
時間・場所を変えて練習!練習!
静かな環境でできるようになったら、今度は時間や場所を変えてやってみましょう。特にお散歩に出かけるときは、タバコの吸殻や食べ物のゴミ名等、犬が口に入れ安そうなものがたくさん落ちています。人通りのあるところ、騒がしい場所でも、きちんと飼い主さんの指示を聞けるようになればトレーニング完了です。
動物病院に行った原因TOP10にランクインしている異物誤飲。(アイペット損保調べ)
飼い主さんがきちんと対策をしていて、危険なものは愛犬の手に届かないところに片付けていても、なかなか減らないのが異物誤飲なのです。
「まさかこんなものを食べるとは・・・。」
「お散歩中にちょっと目を離したすきに・・・。」
異物誤飲対策とあわせて拾い食い防止のトレーニングをすることで、愛犬の健康を守ってあげましょう。
ワンペディアの「食」に関する記事
こちらの記事もあわせてご一読ください。
□ 選び方:「愛犬のために選ぶべきドッグフードとは」
□ 種類:「ドッグフードの種類と正しい選び方」
□ ペットフード安全法:「みんなが買っている市販のドッグフードは
□ 手作りごはん:「実はとっても難しい!
□ 食事管理:「犬に必要な栄養素とは? 食事管理の方法とは?」
□ 管理方法:「食中毒に要注意!暑い時期のフード管理方法」
□ シニアの食事:「シニア犬の食事で気をつけることは?
□ おやつ:「おやつの種類と注意点」
□ 食欲不振:「犬が食欲不振になったとき、どうしたらいいの?
□ NGフード:「犬に与えてはいけない危険な食べ物」
★「うちの子」の長生きのために、気になるキーワードや、症状や病名で調べることができる、獣医師監修のペットのためのオンライン医療辞典「うちの子おうちの医療事典 」をご利用ください。
下記のような切り口で、
【治療面】■ 再発しやすい ■ 長期の治療が必要 ■治療期間が短い ■ 緊急治療が必要 ■ 入院が必要になることが多い ■手術での治療が多い ■専門の病院へ紹介されることがある ■生涯つきあっていく可能性あり
【対象】■ 子犬に多い ■ 高齢犬に多い ■男の子に多い ■女の子に多い ■ 大型犬に多い ■小型犬に多い
【季節性】■春・秋にかかりやすい ■夏にかかりやすい
【うつるか】 ■ 他の犬にうつる ■ 人にうつる ■猫にうつる
【命への影響度】 ■ 命にかかわるリスクが高い
【費用面】 ■ 生涯かかる治療費が高額 ■手術費用が高額
【愛犬の症状】 □ 元気がない □ 食欲がない □ 食べすぎる □ 水を飲まない □ 水を沢山飲む □ 疲れやすい
ワンペディア編集部からのメールマガジン配信中!
「ワンペディア編集部」では、

アイペット獣医師
詳細はこちら