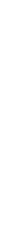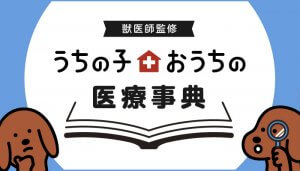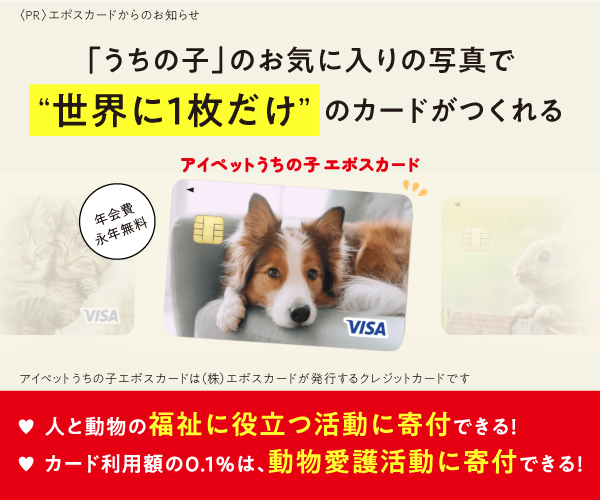犬と暮らす日常の中で、家に犬だけを残して外出しなければならない状況というのは、どうしても避けられません。犬を同伴しての外出ができればいいのですが、すべての施設が犬を受け入れてくれるわけではありませんし、飼い主にとっても行動範囲や活動時間が制限され、ストレスとなりますよね。
飼い主がいなくても、おとなしくお留守番ができれば、安心して家を空けることができます。ですが、留守番のしつけが十分できていないと、ひっきりなしに鳴いたり暴れたり、あるいはストレスから体調を崩したりと、さまざまなトラブルにつながりかねません。
今回は、留守番に際しての飼い主さんの心構えや、しつけのコツについて考えてみましょう。
留守番は、「普通のこと」と認識させる
まず、留守番中に犬が自由に歩き回れる状況にあると、誤飲や誤食、器物の破損やけがなど思わぬ事故へつながる可能性があります。
犬専用の留守番部屋があれば理想
ですが、難しい場合には
サークルの中に犬用の「ハウス」を用意
します。サークルの中にはハウスのほか、トイレ、水、おもちゃなどを置き、留守番の際はそこを定位置と定めます。
次に、上手に留守番ができるようにしつけるためには、犬に留守番は特別なことではないと認識させ、留守番に慣れさせることが必要です。
いきなり長時間の留守番ではなく、最初は例えば5分程度、家を空けます。5分経ったらすぐ家に戻る、という短時間の練習を繰り返し、慣れるのに従って、10分、15分とが外出時間を増やしていきます。こうすることによって、犬は
「なるほど、飼い主さんは勝手に外に出て行き、帰ってくるものなのだな」と認識
していきます。
その際に注意したいのは、バタバタと出かける準備をしたり、声を掛けて別れを惜しむようなそぶりを見せずに、淡々と無言で外出すること。あくまでも、
日常のありふれた生活パターンと思わせる
ことが重要です。同様に帰宅の際も、ごく自然に家に戻り、しばらくはかまわないでいるようにします。
日頃から、犬が1匹だけで過ごす時間を作る
また日頃から四六時中、犬とべったり過ごすことはせず、犬が1匹だけで過ごす時間を意識して作りましょう。一緒に暮らすなかで、ときどき犬の前から姿を消してみてください。
飼い主さんが視界から消え、寂しがって吠えたからといっても、すぐに戻って慰めてはいけません。「吠えると戻ってきてくれる」と学習してしまい、却って逆効果となります。犬が鳴き止んだタイミングを見て部屋に戻り、褒め言葉とともにおやつを与えます。このことにより、犬には「吠えずにじっとしていても飼い主さんは戻ってきてくれる」し「ご褒美ももらえる」という条件付けができるようになります。
ハウスの中におもちゃを入れ、犬が遊んでいる間に部屋を出る、というのも有効です。こうすることで、犬はむしろ
自分だけの時間を楽しく過ごすことを学習
していきます。外出の際にもお気に入りのおもちゃやグッズを用意してあげることで、ひとり遊びを覚えた犬は、留守番の時間も退屈せずに過ごすことができます。
誤飲の対策、室温管理も慎重に
そのほか、留守番の際の飼い主さんの注意点として、
床に誤飲の可能性のあるものを置かない、ゴミ箱の蓋はしっかり閉める
大切なものを壊されないよう、いたずらされそうなものは高い所に片付ける
などの配慮も必要です。
留守番中の部屋の温度管理も重要です。とくに犬は寒さより暑さに弱い動物ですので、夏場の室温には十分注意しましょう。
夏のエアコンの使用は必須
となります。
長時間の外出を予定している場合には、日中の散歩を長めにするなど、しっかり遊ばせてエネルギーを発散
させておきましょう。
犬の留守番は、最大12時間程度を目安に
最後に、犬種や個体にもよりますが、排泄や食事のことを考慮すると、犬に留守番をさせる時間は最大で12時間程度が限度となります。留守番時間がこれを大きく超えるような場合には、ペットホテルやシッターの利用なども視野に入れた方がいいかもしれません。
犬の留守番に関する記事は、こちらをご覧ください。
■クレートを好きになってもらってお留守番上手に【獣医師が解説】
愛犬の行動から、病気の可能性を調べてみる『うちの子おうちの医療事典』
「うちの子」の長生きのために、年齢や季節、犬種など、
例えば、愛犬の「行動」
■ 足をあげる
■ 歩かない
■ 頭を振っている
■ ふらつく
■ ぐるぐる回る
■ 遠吠えをする
■ 性格が変わる

アイペット獣医師
詳細はこちら