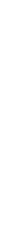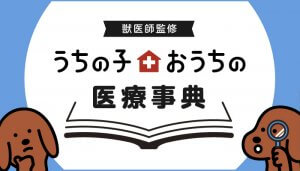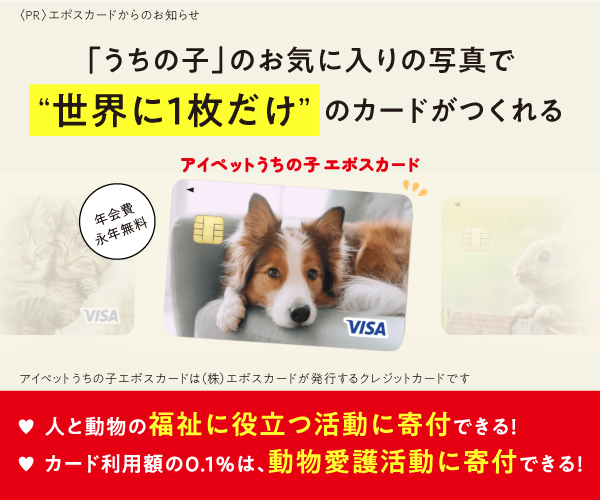愛犬が病気やケガを抱えて生活しなければならない場合に、ご自宅で行うことができるケアについてご紹介します。
在宅酸素室(酸素ハウス)のレンタル
心臓病や肺・気管の病気、貧血、腫瘍の末期症状などにより呼吸が苦しくなってしまう場合、酸素室での入院が必要となることがあります。酸素室は、高濃度の酸素の中で過ごすことで、ワンちゃんの呼吸をサポートしてくれるお部屋のことで、ほとんどの動物病院で備えられている設備です。
近年では、専門業者から家庭用の酸素室をレンタルすることができ、自宅での酸素吸入が可能となることでワンちゃんの呼吸を楽にする大きな助けとなります。
〇 酸素室がどうして必要なの?
動物の体は、呼吸によって空気中の酸素を取り込み、体内の二酸化炭素を外に出します。病気などにより酸素をうまく取り込めなくなると、全身が酸欠状態となり、生命を維持するのが難しくなってしまします。酸素室は、さまざまな原因で酸素をうまく取り込めなくなったワンちゃんに、高濃度の酸素環境を提供することで、呼吸をサポートする設備です。
通常の環境下では十分な酸素を取り込めず、呼吸困難になってしまう動物でも、酸素濃度の高い空気を吸うことで、効率よく酸素を体内に取り込むことができます。人では酸素マスクを使用することが多いですが、犬や猫ではマスクを装着し続けることが難しいため、ケージ内の酸素濃度を高める酸素室が適しています。
〇 在宅酸素室のしくみ
使い方はメーカーにより多少異なりますが、基本的には、お部屋の空気から高濃度の酸素をつくり出す酸素濃縮器と、酸素を溜めるケージをホースでつなぎ、電源を入れることでケージ内の酸素濃度が高まります。在宅酸素室には、購入とレンタルがあり、サイズも動物の大きさに合わせて選択することができます。
〇 注意点
酸素室内の酸素濃度や温度・湿度管理が重要です。設置をする際にしっかりと説明を受け、ご自宅での設置場所や使い方を確認しましょう。
酸素室が必要なワンちゃんは、酸素室から出すと呼吸が苦しくなってしまうので、基本的には酸素室内で生活することをおすすめします。
食事や排泄の介助、投薬などで酸素室から出す場合には、呼吸状態に注意して、愛犬から目を離さないようにしましょう。呼吸が速く苦しそうになったり、舌が青紫色になったりする(チアノーゼ)場合には、速やかに酸素室内に戻しましょう。

自宅での皮下点滴
皮下点滴とは、皮膚の下に針を刺して点滴用の輸液剤を注入する方法です。人間の点滴でイメージされる静脈点滴は血管に針を入れて少しずつ点滴を行いますが、皮下点滴は血管ではなく背中などの皮膚の下に針を入れて輸液剤を注入し、注入された液体は数時間かけて皮膚の下から体内にゆっくりと吸収されるしくみです。
皮下点滴のメリットは、短時間(およそ10〜20分程度)で実施することができることや、静脈点滴とは違い入院の必要がなく、ご自宅でも実施することができることです。
〇 どんなときに皮下点滴をするの?
皮下点滴をが必要となるのは以下のような場合です。
・脱水しているとき
・食欲や活動性がない、または低下しているとき
・血流を改善したいとき
など
とくに慢性腎臓病や、がん、高齢犬で食欲や活動性が低下しているときなどに、在宅での定期的な皮下点滴が治療の選択肢となることがあります。
〇 注意点
心臓病がある場合や、胸水・腹水が溜まっている場合、体のどこかが浮腫んでいる場合には、皮下点滴をすることで体内の水分が過剰となり、呼吸などに影響する危険性があるため注意が必要です。
皮下点滴を行う前には、獣医師から点滴のつなぎ方や針の刺し方、点滴の量や速度について十分な説明を受けましょう。点滴中に動物が暴れてしまうと危険なため、可能であればご家族で協力して行うとより安全です。
使用済みの針などは、動物病院の指示に従い適切に処理しましょう。

寝たきりのケア
高齢や病気で寝たきりになった場合、褥瘡(床ずれ)の予防や排泄のケアが重要になります。
とくに褥瘡は一度できてしまうと管理が難しいことが多いので、予防を心がけましょう。
〇 褥瘡とは?
褥瘡(じょくそう)は、皮膚の同じ部分に長時間圧力がかかることで、皮膚やその下の組織が壊死してしまう皮膚の病気です。褥瘡は、加齢や老衰、麻痺、起立不全など、体を自由に動かすことができない状態で問題となることが多く、とくに大型犬では重症化しやすいため、注意が必要です。
褥瘡ができる前段階として、その部分に脱毛が起きることが多いので、体を自由に動かせない愛犬が部分的に脱毛を起こしたら要注意。悪化しないように、以下のようなケアをしてあげましょう。
① 環境の改善
褥瘡ができてしまう原因は、皮膚の同じ部分に長時間圧力がかかることなので、圧力を逃がすような工夫をすることが大切です。
硬い床で寝ていたり、普段使用しているベッドやクッションが硬いものの場合には、褥瘡ができやすくなってしまします。反対に、薄すぎたり柔らかすぎるクッションでは、体重のかかる部分が沈み込んで床につきやすくなってしまうため、褥瘡防止用のクッションや、介護用のベッドなどを使用すると良いでしょう。
②こまめな体位変換
褥瘡は同じ姿勢で長時間いることが原因となるため、こまめに体位変換をしてあげることが予防につながります。目安として、1〜4時間ごとに体の向きを変えてあげましょう。体位変換をするときには、ワンちゃんの状態をよく見ながら、無理のない範囲で優しく行いましょう。
③ 清潔を保つ
排泄物で体が汚れると、褥瘡の悪化につながります。尿や便の上で寝てしまうことのないよう、排泄物はこまめに取り除いて掃除をし、体に付着してしまった場合には洗浄するなどして清潔に保ちましょう。
④ 褥瘡のケア
褥瘡を犬が舐めたり擦ったりしてしまうと悪化につながります。そのため、褥瘡ができてしまった場合には、はやめに動物病院を受診しましょう。部位によってはエリザベスカラーを装着したり、感染を起こしている場合には、傷の消毒や抗生剤を使用する場合もあります。

徘徊への対応
高齢犬では、認知機能不全などで夜中に徘徊したり、不安そうに鳴いたりすることがあります。
投薬治療により症状が改善する場合もありますが、徘徊する場合には以下のことに気をつけましょう。
・家具や物にぶつかって怪我をしないよう、危険な物を片付けたり、段差をなくすようにしましょう。
・事故などを防ぐために、極力飼い主さんの目の届く場所で過ごさせましょう。
・高齢になると日中に寝ている時間も長くなりがちです。日中に適度な刺激を与え、夜は体をゆっくり休められるような生活リズムを整えることも大切です。
強制給餌
病気などで食欲がない場合、栄養補給のためにシリンジやスポイトなどを使って強制的に食事を与える「強制給餌」が必要になることがあります。
与えるフードの種類は病気や年齢によって異なります。フードの量・回数・与え方についても、必ず獣医師の指示を仰ぎましょう。
強制給餌で最も気をつけなければならないのは、誤嚥です。誤嚥を起こさないよう、与える際は少量ずつ、ゆっくり焦らず、犬が嫌がらない範囲で行うことが重要です。

このように、病気やけがの動物に対して在宅でも行えるケアにはさまざまな方法があります。
在宅ケアを行う場合には、かかりつけの獣医師と密に連携をとり、不安なことや愛犬に変化があれば速やかに相談しましょう。食事の量や排泄の有無などは、記録をつけるとケアや治療の一助になる場合があります。
在宅ケアは、ときには大変なこともありますが、愛犬との穏やかな時間を過ごせる貴重なひとときでもあります。すべてのケアを完璧に行う必要はありません。飼い主さんが疲弊してしまうと、かえってわんちゃんにもストレスがかかったり、通院が困難になってしまっては本末転倒です。まずは無理のない範囲から始めてみましょう。何か不安なことや、うまくできないことがあれば、抱え込まずに動物病院で相談してみましょう。
★ うちの子おうちの医療事典
気になる症状や病名から病気のことを簡単に調べられる、ワンちゃん・ネコちゃんのための「うちの子おうちの医療事典」。うちの子の健康のために、ぜひご活用ください!
★ワンペディア編集部からのメールマガジン配信中!
「ワンペディア編集部」では、愛犬との暮らしに役立つお勧め記事や、アイペット損保からの最新情報を、ワンペディア編集部からのメールマガジン(月1回第3木曜日夕方配信予定)でお知らせしています。ご希望の方はこちらからご登録ください。